結論ですが、
ダニエルズ式の5つのペースとして「E(Easy)ペース」「M(Marathon) ペース」「T(Thresold)ペース」「I(Interval)ペース」「R(Repetition)ペース」があります。
この記事は「マラソンを楽しんでいるヒト」に向けて書いています。
マラソントレーニングに関する疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「ダニエルズ式の5つのペース」についてわかります。
マラソンをやっていますが、どのようなトレーニングがいいですか?
このような疑問にお答えします。
自分自身、ランニングが趣味でして、時間があれば走っています。
そして、マラソン大会によく出ています。
地元開催のマラソンや、北海道内のマラソン、東京や関東圏などの様々なマラソン大会に出場させて頂いております。
マラソン大会に向けて、日々トレーニングにのぞんでいるかと思います。
毎日同じようなトレーニング内容だと飽きてしまうかと思います。
また、能力に偏りが生じてしまい、どこかで頭打ちになってしまうかと思います。
マラソントレーニングとして有名なものに「ダニエルズ式トレーニング」があります。
ダニエルズ式では「VDOT」という指標が使われます。
「VDOT」とは、VOmax(最大酸素摂取量)に1分間当たりという意味を加えたものであり、簡単にいうと「1分間当たりの最大酸素摂取量」ということになります。
VDOTの値が高いほど、有酸素運動に優れているため、マラソンのタイムと相関します。
ダニエルズ式では、VDOTによって、ランナーの走力をレベル分けし、それぞれにあった練習ペースの目安を示してくれます。
そこで登場するのが「ダニエルズ式の5つのペース」になります。
では、ダニエルズ式の5つのペースとは何ですか?
ということで、今回は「ダニエルズ式の5つのペース」について説明します。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/
まとめ
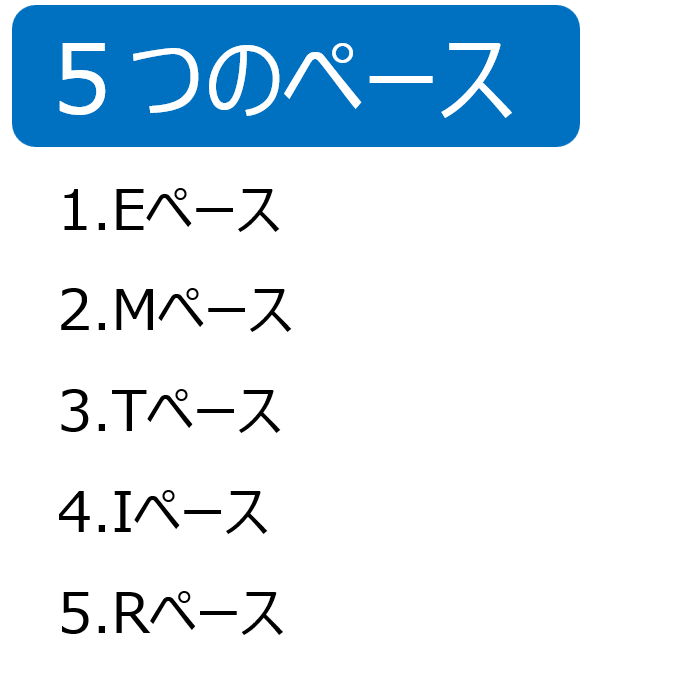
1.Eペース
ダニエルズ式の5つのペースとして「Eペース」があります。
Eは「Easy」の略であり、気持ちの良いペースということになります。
強度はVO2maxの59〜74%で、HRmaxの65〜78%であり、会話をしながらでも走れるようなスピードです。
サブ3ランナーでは、「4’38”/km~5’14”/km」くらいのペースです。
「つなぎのジョグ」「疲労抜きのジョグ」などだけでなく、「距離走」などの長い時間のジョグ、「ペースジョグ」などの速めのジョグをする時などにEペースが目安になります。
Eペースのトレーニングを「酸素、栄養、筋肉」の観点からみてみます。
「酸素」の観点でいうと、毛細血管の発達、長時間の持続的な運動によって心肺機能が向上します。また、心筋や血管の平滑筋にも低出力の負荷が長時間かかるため、それらを鍛えることにつながります。
「栄養」の観点でいうと、長い時間の運動を続けるため、脂質代謝が促されやすくなります。
「筋肉」の観点でいうと、低出力・高回数の運動になるため、超長時間耐えうる筋持久力の向上につながります。
ダニエルズ式の5つのペースとして「Eペース」があります。
2.Mペース
ダニエルズ式の5つのペースとして「Mペース」があります。
Mは「Marathon」の略であり、フルマラソンのレースを走るときのペースということになります。
サブ3ランナーでは、「4’14”/km」くらいのペースです。
Mペースのトレーニングを「酸素、栄養、筋肉」の観点からみてみます。
「酸素」の観点でいうと、毛細血管の発達、心肺機能の向上、マラソンレースペースへの最適化などがあります。
「栄養」の観点でいうと、糖質代謝・脂質代謝のマラソンレースへの最適化、補給の練習などがあります。
「筋肉」の観点でいうと、マラソンのレースペースにおけるフォームの獲得などがあります。
ダニエルズ式の5つのペースとして「Mペース」があります。
3.Tペース
ダニエルズ式の5つのペースとして「Tペース」があります。
Tは「Threshold」の略であり、乳酸の再利用が追いつかず体内に蓄積される強度である「閾値」ペースのことであり、「LT」と同じ意味になります。
強度はVO2maxの86〜88%で、HRmaxの88〜90%です。
サブ3ランナーでは、「4’00”/km」くらいのペースです。
Tペースのトレーニングを「酸素、栄養、筋肉」の観点からみてみます。
「酸素」の観点でいうと、酸素需要が高まるためミトコンドリアの発達、心肺機能の向上、最大酸素摂取量の向上などがあります。
「栄養」の観点でいうと、糖質代謝の促進、乳酸の再利用促進などがあります。
「筋肉」の観点でいうと、レースペースより速いペースのフォーム獲得、耐乳酸能力、筋持久力の向上などがあります。
ダニエルズ式の5つのペースとして「Tペース」があります。
4.Iペース
ダニエルズ式の5つのペースとして「Iペース」があります。
Iは「Interval」の略です。インターバルトレーニングは「速いスピード」と「遅いペース」を繰り返す方法で行われるトレーニングです。
主に5000mのトレーニングで用いられる「400m〜1000m」程度の距離を基準としたインターバルを走り切るくらいのペースになります。
強度はVO2max、HRmaxの100%です。
サブ3ランナーでは、「3’41”/km」くらいのペースです。
Iペースのトレーニングを「酸素、栄養、筋肉」の観点からみてみます。
「酸素」の観点でいうと、単位時間あたりの酸素需要が一気に高まるためミトコンドリアの発達、心肺機能の向上、それにともなう最大酸素摂取量の向上などがあります。
「栄養」の観点でいうと、糖質代謝の促進、乳酸の再利用促進などがあります。
「筋肉」の観点でいうと、レースペースより速いペースのフォーム獲得、耐乳酸能力、筋持久力の向上などがあります。
ダニエルズ式の5つのペースとして「Iペース」があります。
5.Rペース
ダニエルズ式の5つのペースとして「Rペース」があります。
Rは「Repetition」の略です。速いスピード域に達して走るため1km走り切れるかどうかのペースです。
走る距離は「200m〜400m」程度であり、かなりスピードを上げて走ることになります。1本1本フォームが崩れないようにすることが重要であり、十分なレストを取る必要があります。Rペースで走った時間の2〜3倍のレスト、またはRペースで走った距離と同じ距離のジョグをすることが推奨されています。
サブ3ランナーでは、「3’25”/km」くらいのペースです。
Rペースのトレーニングを「酸素、栄養、筋肉」の観点からみてみます。
「酸素」の観点でいうと、酸素需要が一気に高まり供給が追いつかないため、無酸素性能力の向上があります。
「栄養」の観点でいうと、糖質代謝の促進、無酸素性代謝の促進、乳酸の再利用促進などがあります。
「筋肉」の観点でいうと、レースペースより速いペースのフォーム獲得、ランニングエコノミーの向上などがあります。
ダニエルズ式の5つのペースとして「Rペース」があります。
まとめ
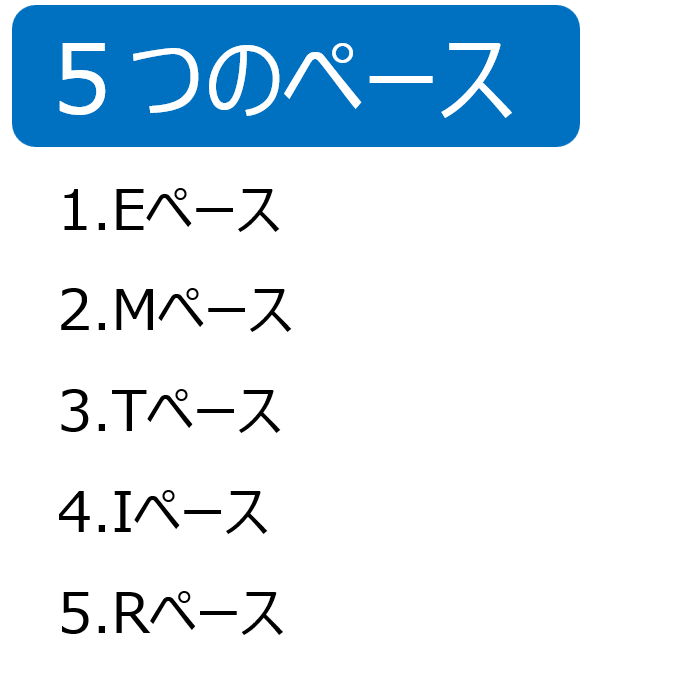
今回は「ダニエルズ式の5つペース」について説明しました。
この記事によって「ダニエルズ式の5つペース」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/















コメントを残す