結論ですが
筋肉を目的としたトレーニングとして「筋力トレーニング」「距離走」「動き作り」などがあります。
この記事は「マラソンを趣味にしている」ヒトに向けて書いています。
トレーニングに対する疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「筋肉を目的としたトレーニング」についてわかります。
酸素を目的としたトレーニングにはどのようなものがありますか?
このような疑問にお答えします。
自分自身、ランニングが趣味でして、時間があれば走っています。
そして、マラソン大会によく出ています。
地元開催のマラソンや、北海道内のマラソン、東京や関東圏などの様々なマラソン大会に出場させて頂いております。
マラソン競技を行っていて、「酸素」「栄養」「筋肉」の3要素が重要だと考えています
「酸素」「栄養」からエネルギーが生み出され、そのエネルギーが「筋肉」で使われ、パフォーマンスが発揮されます。
そのうち、筋肉についてピックアップします。
では、筋肉を目的としたトレーニングにはどのようなものがありますか?
ということで、今回は「筋肉を目的としたトレーニング」について説明していきます。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/
まとめ
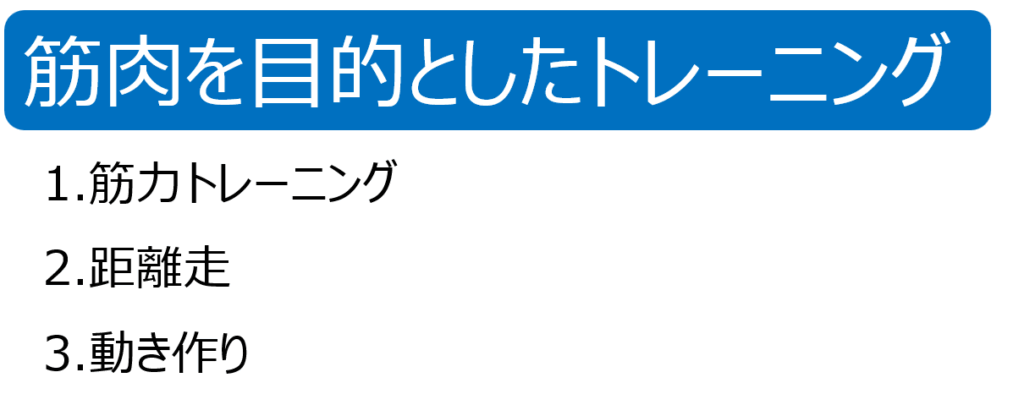
1.筋力トレーニング
筋肉を目的としたトレーニングとして「筋力トレーニング」があります。
筋力トレーニング(筋トレ)とは、特定の筋肉に負荷をかけて筋力を向上させる運動であり、
最大筋力や筋持久力などの向上を目的とします。
ランナーにとって、筋力トレーニングによって、走りの動作に関係する筋力を向上することができます。とくに、より長い時間、より長い距離を走り続けるために「筋持久力」が大切であり、筋トレで向上させることができます。
また、筋力が高まると、走りのフォームが安定しますし、スポーツ障害などのケガの予防につながります。
ランナーにオススメの筋力トレーニングは「走る動作に関係する筋肉」を鍛えることです。
とくに、下半身の大殿筋・ハムストリングス・大腿四頭筋・腓腹筋・ヒラメ筋・股関節屈筋、上半身の腹筋(体幹部)・背筋・脊柱起立筋(背骨)などの筋肉が重要です。
「スクワット」「デッドリフト」「ランジ」「プランク」「カーフレイズ」などの種目がオススメです。
また、ランナーは、筋肥大による体重増加を避けながら、筋力を高めることが大切になります。筋肥大させないように、最大筋力向上を目的とする「高負荷・低回数」や、筋持久力向上を目的とする「低負荷・高回数」による筋力トレーニングがオススメです。
2.距離走
筋肉を目的としたトレーニングとして「距離走」があります。
距離走は、20kmから40km程度の長い距離を一定のペースで走るトレーニングです。
ゆっくり長く走る「LSD」(Long Slow Distanse)も距離走の一つとされる場合もあります。
また、長い距離をペースの変化をつけて走る「変化走」や、後半に徐々にペースアップをする「ビルドアップ走」、徐々にペースダウンをする「ビルドダウン走」など長い距離を走る場合、「距離走」というカテゴリーに入る場合もあります。
距離走では、とても長い距離を走ることになるため、究極的な「低負荷・高回数」の筋力トレーニングになります。
そのため、「走る動作に関係する筋肉」に対する筋持久力の向上につながります
他にも、毛細血管が発達し、筋肉などに効率的に酸素を供給できるようになりますし、「脂質代謝」が促され、長時間運動を続けるためのエネルギーの持続性が高まります。
さらに、長い距離の運動に慣れることができ、フルマラソンの距離への不安が軽減できます。
距離走の距離は、20kmから40km程度が目安になります。
しかし、慣れない最初のうちは、10kmからはじめて、次は15km、その次は20kmという具合に徐々に距離を伸ばしていき、最終的に40kmまでいけたら良いかと思います。
走るペースとして、はじめは無理をせずゆっくりと景色を楽しむくらいのペースで走る「LSD」(Long Slow Distanse)からはじめるのが良いでしょう。
慣れてきたら、徐々にペースを上げていき、easy jogペース、Eペース、最終的にはマラソンのレースペースである「Mペース」くらいまで上げられると良いでしょう。
本番のマラソンのレースの前には、距離は短めにして、なるべくレースペースと同じくらいの速さで走り、リハーサルの位置づけにすることもできます。
3.動き作り
筋肉を目的としたトレーニングとして「動き作り」があります。
動き作りによって、いわゆる「筋神経系」を研ぎ澄まされます。
効率的なランニングフォームを獲得できると、ランニングエコノミーが向上し、より少ないエネルギーで効率的に走ることができます。
動き作りの方法として「ドリル」「プライオメトリック運動」「坂ダッシュ」「ウインドスプリント」などがあります。
1.ドリル
ドリルは、走りの動作の一部をピックアップしてトレーニングする方法です。
様々な動きを取り入れて、自分にとって最適な走るフォームを身につけるために、ドリルを行います。
たとえば…
もも上げ
バウンディング
トロッティング
スキップ
ハイニースキップ
ギャロップ
などの種目があります。
走る動作の要素を分解して確認することができます。
さらに、足の動かし方・さばき方・反発の感覚など脳に様々な刺激が入るため、筋神経系を研ぎ澄ます効果が期待できます。
メインの練習を行う前に、ドリルを取り入れて、良い動きを頭に入れてから本練習を行うと良いでしょう。
2.プライオメトリック運動
プライオメトリック運動では、伸張反射をうまく利用するトレーニングとなり、主にジャンプ系の動きをして行われます。
伸張反射とは、筋肉が引き伸ばされることによって、力を入れる意識をしなくても自然と筋肉が収縮する現象のことを言います。
筋肉の中でも「筋紡錘」という構造がある筋肉において起こります。
とくに、走る動作に関係する筋肉において、
股関節の屈曲に関係する「大腿四頭筋」
股関節の伸展に関係する「ハムストリングス」
足関節の屈曲に関係する「下腿三頭筋」(ヒラメ筋・腓腹筋)
などの筋肉が重要です。
プライオメトリック運動では、接地する時に伸ばされた筋肉が、伸張反射によって収縮し、跳ぶ動作につなげることができます。
伸張反射による筋収縮や、全身の筋肉の協調運動などを利用して、より高く跳ぶようにすることで、接地局面の感覚を磨くことができます。
ジャンプトレーニングは、足への衝撃がくるため、できるだけ土や芝の上で行いましょう。
また、ボックスジャンプや、ハードルジャンプ、ラダーなどを使用してアレンジしてもいいでしょう。
3.坂ダッシュ
坂ダッシュでは、上り坂をダッシュして駆け上がります。
平地と違って、走りの動きに無駄があると、うまくスピードにのせて走ることができません。
とくに、
重心移動をスムーズにする
腕振りをしっかりとする
接地局面で膝を前に出そうとする
などを意識すると良いでしょう。
坂ダッシュは、だいたい、50m~150mくらいの距離を、3~10本程度おこないます。
追い込む練習ではなく、あくまで走りのフォームを確認するのが目的なので、しっかりとリカバリーして一本一本集中して取り組みましょう。
4.ウインドスプリント
ウインドスプリントは、8割くらいの力で、気持ちいいと感じる心地の良いスピードで走ることであり、「流し」などとも呼ばれます。
ウインドスプリントでは、だいたい50m-150mくらいの距離を走ります。
余裕のあるスピードで、フォームを意識して走ることができます。
追い込む練習ではなく、あくまで、走りのフォームを確認するのが目的なので、しっかりとリカバリーして一本一本集中して取り組みましょう。
本番のトレーニングの前のウォーミングアップとして取り入れてもいいですし、
トレーニングの最後に、動きの確認をするために行ってもいいでしょう。
まとめ
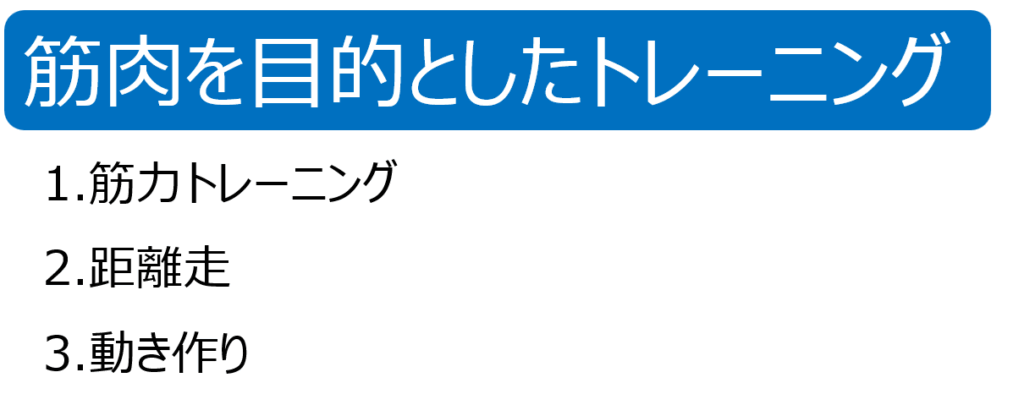
今回は「筋肉を目的としたトレーニング」について説明しました。
この記事によって「筋肉を目的としたトレーニング」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/













コメントを残す