結論ですが
筋肉と肝臓は、働きが似ていますし、お互いに関係しあっています。
この記事は「健康について興味あるヒト」に向けて書いています。
健康に対する疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「筋肉と肝臓の関係性」についてわかります。
筋肉と肝臓にはどのような関係がありますか?
このような疑問にお答えします。
ということで、今回は「筋肉と肝臓の関係性」について説明していきます。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/
まとめ
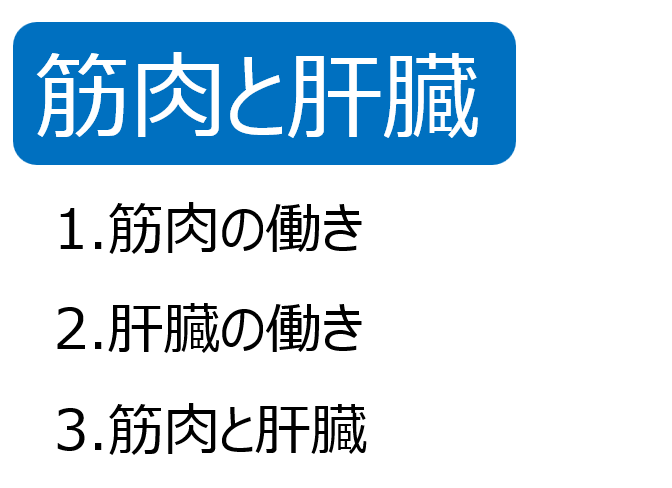
1.筋肉の働き
筋肉の働きとして「体を動かす」「内臓を保護する」「体温の維持」「血液を循環させる」「エネルギー代謝」「エネルギー貯蔵」などがあります。
筋肉が伸びたり縮んだりすることで、関節を曲げたり伸ばしたりして体を動かすことができます。立つ、歩く、走る、座る、呼吸・発声・食事などの動作を行うためには筋肉が必要です。
また。骨格筋は、血管や神経、内臓などを外部の衝撃から守るクッションの役割を担っています。
筋肉は、熱エネルギーを生み出し、体温を一定に保つ役割があります
筋肉の収縮によって、全身に巡った血液を心臓に戻すポンプの役割を果たしています。とくに、
ふくらはぎの筋肉は第二の心臓ともよばれ、筋収縮のポンプ作用によって、足の末梢にたまった血液を全身に送る働きをしてくれます。
また、筋肉では糖質や脂質などからエネルギーを産生します。エネルギー源として利用されずに余った糖質はグリコーゲンという形で、筋肉に貯蔵されます。
2.肝臓の働き
肝臓の働きとして「エネルギー代謝」「エネルギー貯蔵」「体温の維持」「タンパク質の合成」「解毒作用」などがあります。
肝臓では、体内に取り込まれた糖質・脂質・タンパク質などの栄養素を分解して、エネルギーを産生する働きがあります。
エネルギー源として利用されずに余った糖質はグリコーゲンという形で、肝臓に貯蔵されます。
また、余った脂質は体脂肪として皮下脂肪や内臓脂肪として貯蔵されますが、肝臓にも貯蔵される場合があり「脂肪肝」とよばれます。
肝臓で産生されたエネルギーは、体を動かす「運動エネルギー」にもなりますし、体温を一定に保つための「熱エネルギー」にもなります。
肝臓では、摂取した食べ物が消化吸収され運ばれてきた「アミノ酸」を材料にして、タンパク質を合成し、全身に必要なタンパク質を血液を通じて送ります。
肝臓では、体内に取り込まれた有害物質を分解・無毒化し、尿や胆汁などに排泄する働きがあります。
たとえば、お酒などから摂取された「アルコール」は、肝臓において「アセトアルデヒド」と「酢酸」に分解して、最終的には「二酸化炭素」と「水」にして体外に排出します。
また、タンパク質を構成する「アミノ酸」をエネルギー源として使用される場合、アミノ基から「アンモニア」が産生されますが、尿素にして尿として体外に排出します。
肝臓の働きとして「エネルギー代謝」「エネルギー貯蔵」「体温の維持」「タンパク質の合成」「解毒作用」などがあります。
3.肝臓と筋肉
肝臓と筋肉には、似たような働きがありますし、お互いに関係しあっています。
筋肉と肝臓は、「エネルギー代謝」「エネルギー貯蔵」「体温保持」「解毒作用」など似たような働きがあります。
とくに、筋肉では実はアンモニアの解毒作用もあり、筋肉は「第二の肝臓」とも呼ばれます。
また、筋肉と肝臓の関係でいうと、肝臓の病気を持っている方は、健康な人よりも筋肉量が減少しやすいです。これは、肝臓でのタンパク質を合成する働きが弱ってしまうためです。
さらに、筋肉量が減少すると肝臓の病気も悪化しやすいため、肝臓の病気を持っている患者に対する運動療法が重要になります。
なお、筋肉を増やすことで脂肪肝を改善することができます。
肝臓と筋肉には、似たような働きがありますし、お互いに関係しあっています。
まとめ
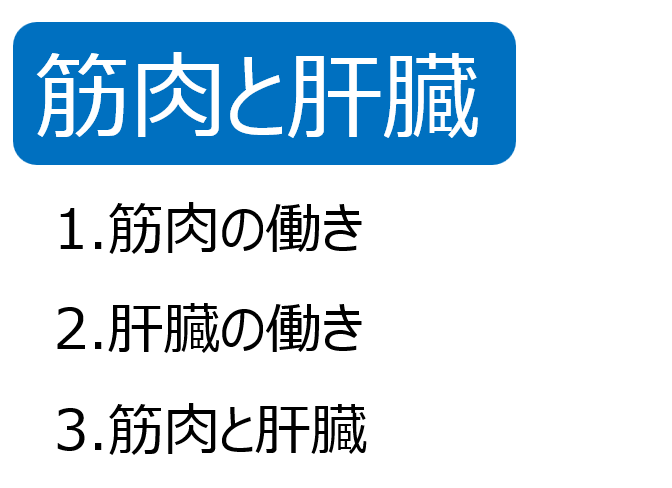
今回は「筋肉と肝臓」について説明しました。
この記事によって「筋肉と肝臓」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/


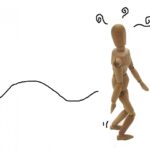


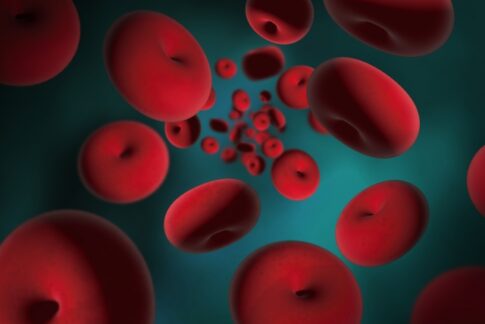
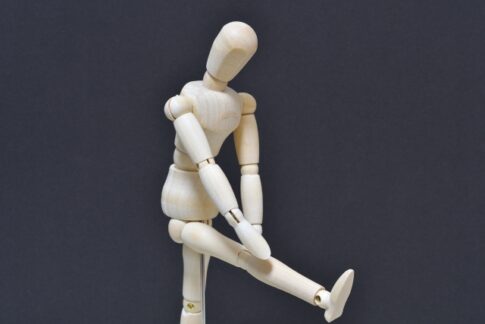






コメントを残す