結論ですが
マラソン競技において、「酸素」「栄養」「筋肉」の3つの要素が重要です。
この記事は「マラソンを趣味にしている」ヒトに向けて書いています。
トレーニングに対する疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「酸素、栄養、筋肉」についてわかります。
マラソン競技において重要な要素は何ですか?
このような疑問にお答えします。
自分自身、ランニングが趣味でして、時間があれば走っています。
そして、マラソン大会によく出ています。
地元開催のマラソンや、北海道内のマラソン、東京や関東圏などの様々なマラソン大会に出場させて頂いております。
マラソン競技を行っていて、「酸素」「栄養」「筋肉」の3要素が重要だと考えています
「酸素」「栄養」からエネルギーが生み出され、そのエネルギーが「筋肉」で使われ、パフォーマンスが発揮されます。
そして、日々のマラソントレーニングを行っていますが、必ずトレーニングの目的を意識しています。
このときに、酸素・栄養・筋肉の3つの観点で考えることが大切だと考えます。
マラソン競技において、酸素・栄養・筋肉がなぜ重要なのですか?
ということで、今回は「酸素、栄養、筋肉」について説明していきます。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/
まとめ
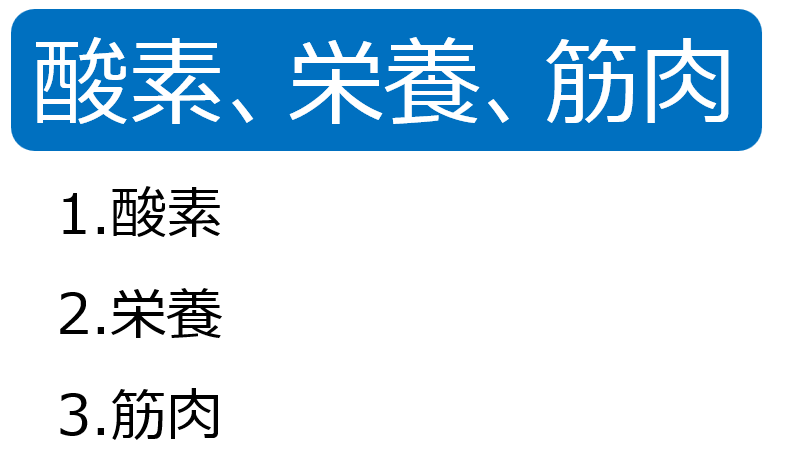
1.酸素
マラソン競技において「酸素」の要素が重要です。
酸素を使える量が多くなれば、産生するエネルギーが増え、マラソン競技のパフォーマンス向上につながります。
マラソン競技において、筋肉が長時間動き続けるためには、多くのエネルギーが必要です。
「糖」や「脂質」などのエネルギー源から、エネルギーを生み出して、筋肉は動きます。
短時間の運動であれば、酸素を利用しない無酸素性エネルギー代謝によるエネルギー産生で間に合うかもしれません。
しかし、マラソンなどの長時間の持久系競技では、それだけではエネルギーの量は不十分です。
そこで、酸素を利用する有酸素性エネルギー代謝によって、より多くのエネルギーを生み出すことが必要になります。
たとえば、グルコース(ブドウ糖)からエネルギーを生み出す場合…
「グルコース+酸素→二酸化炭素+水+エネルギー」
という式で表されます。
少し難しい式でいうと…
「C₆H₁₂O₆+6O₂+34(36)ADP+34(36)Pi→6CO₂+6H₂O+34(36)ATP」
という式になり、酸素を使う量が多ければ多いほど、ATPの産生量、つまり生み出されるエネルギーは増えるのです。
使える酸素の量が多くなり、産生するエネルギーが増えると、マラソン競技において、より速く、より長く、走り続けることにつながります。
マラソンのパフォーマンスの向上、つまりタイムを少しでも良くするためには、利用できる酸素の量を多くし、より多くのエネルギーを産生することが重要です。
2.栄養
マラソン競技において「栄養」の要素が重要です。
我々の体は、食べたものをエネルギーに変えて、体を動かしています。
栄養が足りないと、エネルギーを生み出すことができず十分に動かすことができません。しっかりと食事を摂り、より多くのエネルギーを生み出すようにすることが重要です。
「糖質」「脂質」「タンパク質」は、三大栄養素とよばれ、エネルギー源となる栄養素です。
マラソン競技におけるエネルギー源は「糖質」と「脂質」が大切であり、「タンパク質」を出来るだけエネルギー消費させないことが大切です。
「糖質」は「1g当たり約4kcal」のエネルギーがあります。
糖質は、エネルギー源としてすぐに利用されやすく、出力が高い運動で優先的に使われます。しかし、グリコーゲンとして貯蔵される量は「約1600kcal」程度と少ないです。
一方、「脂質」は「1gあたり約9kcal」のエネルギーがあります。
脂質は、エネルギー源として利用されるまでに時間がかかりますが、出力が低く、長時間の運動を続けるときに安定的にエネルギーを供給してくれます。
脂質は体脂肪として蓄えられますが、貯蔵量は膨大にあり、体重60kg・体脂肪率12%の方では「約50000kcal程度」になります。
マラソン競技において、糖質と比べて利用されにくい脂質をエネルギー源として使い、糖質をいかに温存するかという観点も重要になります。
ちなみに、「タンパク質」は「1gあたり約4kcal」のエネルギーがあります。
糖質や脂質からのエネルギーが足りないときに、「糖新生」などによって、エネルギーとして利用されます。
マラソン競技では、長い時間の運動を続けるためにエネルギーが必要になります。
とくに糖質・脂質によるエネルギーが大切になるので、しっかりとエネルギー源を確保するように意識しましょう。
3.筋肉
マラソン競技において「筋肉」の要素が重要です。
「筋力」(最大筋力や筋持久力)が向上すると、マラソン競技において、より速く、より長く走ることができます。
また、「筋神経系」を研ぎ澄まし、ランニングエコノミーが向上すると、より少ないエネルギーで効率的に走ることができます。
マラソン競技などの持久系競技においては、筋肉が持続的に動くために「筋持久力」が重要です。
フルマラソンでは「42.195km」という、とてつもなく長い距離を「走る動作」を持続することになるため「筋持久力」を高めることが大切です。
一方、生み出されたエネルギーを、いかにして効率的に走りに活かすかという観点も必要になります。
エネルギー効率が良い「ランニングフォーム」、いかに省エネで走るかという「ランニングエコノミー」も大切になります。
運動をするときには、脳からの指令が神経を通じて筋肉に到達して筋肉は動きます。
このときの、「脳」→「運動神経」→「筋肉」のルート、つまり「筋神経系」が重要になるのです。
効率の良い走りを実現するためには、走りに関係する筋肉が正しく収縮と伸展をおこない、複数の筋肉がうまく連携し協調運動しながら、「走る動き」を作り上げることになります。
まとめ
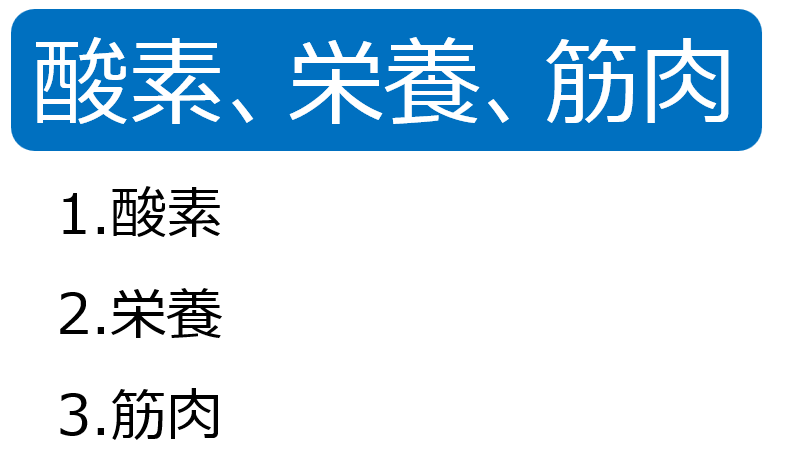
今回は「酸素、栄養、筋肉」について説明しました。
この記事によって「酸素、栄養、筋肉」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/















コメントを残す