結論ですが、
糖質を摂取するポイントとして「糖質の摂取量」「糖質の種類」「GI値」などがあります。
この記事は「アスリートの栄養について知りたいヒト」に向けて書いています。
アスリートへの疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「糖質を摂取するポイント」についてわかります。
糖質を摂取するときには、どのようなポイントがありますか?
このような疑問にお答えします。
糖質は、体を動かすためのメインのエネルギー源となります。また、脂質をエネルギー源として使う時にも糖質の存在は必要になります。
しっかりと糖質を補給することによって、産生するエネルギーが多くなり、出力は上がるため、トレーニングの質が上がります。
反対に、糖質などのエネルギー源が不足すると、出力が低下し、トレーニングの質は下がってしまいます。いくらトレーニングを行っても、思うような成果に結びつかないのです。
ただし、糖質の摂り過ぎは糖尿病につながるため、適切な量を心がけることが大切です。
では、糖質を摂取するときには、どのようなポイントがありますか?
ということで、今回は「糖質を摂取するポイント」について説明していきます。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/
まとめ
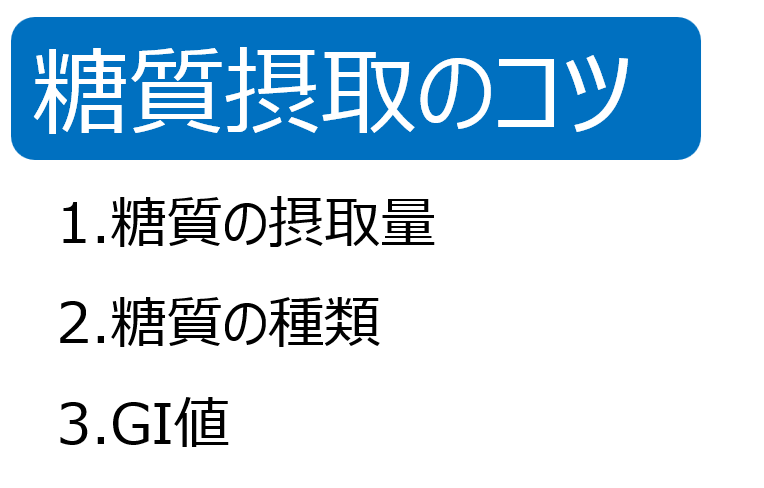
1.糖質の摂取量
糖質を摂取するポイントとして「糖質の摂取量」があります。
アスリートの糖質摂取量は、1日に必要なエネルギーの60%以上が望ましいとされています。
また、体重1kgあたり6~10gの糖質を摂取することも推奨されています。
ちなみに、体重60kgの場合、必要な糖質量は「360~600g」となり、「1440~2400kcal」に相当します。
白米100gあたり糖質は「約35g程度」含まれるため、「白米1kg~1.7kg」に相当します。
強豪校では、白米を1日2kg以上食べるように指導されるケースもありますが、体格の良い選手であればそのくらいの量になります。
これは、あくまで糖質の摂取量の目安であり、競技内容やトレーニング内容、トレーニング時期、それぞれの身長・体重などの体格によって、糖質を摂取すべき量は異なります。
なお、強度の高い運動後には、枯渇した糖質を補給するために、
1時間以内に体重1kgあたり「約1~1.2g」
4時間以内に体重1kgあたり「約1~1.2g/1時間」程度の糖質を補給すると効果的です。
競技時間が長時間に及ぶ持久系スポーツでは、パフォーマンス維持のために、
競技中に「約60g/1時間」程度の糖質を摂取することがすすめられています。
糖質を摂取するポイントとして「糖質の摂取量」があります。
2.糖質の種類
糖質を摂取するポイントとして「糖質の種類」があります。
糖質の種類として「単糖類」から「二糖類」「少糖類(オリゴ糖)」「多糖類」などがあります。
これらの順番に結びついている分子の数が多くなっていき、消化までの時間が遅くなっていきます。
つまり、「単糖類」が一番消化が早く、「多糖類」が消化に時間がかかります。
なお、単糖類の中でも「果糖」は、すぐにエネルギーとして利用されやすく、インスリン分泌と関係ないため、反発性の低血糖が起こりにくいため、運動前の糖質摂取でオススメします。
一方、単糖類の「ブドウ糖」は、血液中のブドウ糖濃度が上昇(血糖値が上昇)し、インスリンが分泌されて、細胞内にブドウ糖が取り込まれて利用されるとともに、血糖値は低下します。
糖質を摂取するタイミングが悪いと、トレーニング中に低血糖を起こしてしまう「大福餅症候群」が起こる可能性があるため注意が必要です。
多糖類であるデンプンを含む「ごはん」や「小麦(パン・パスタ・うどんなど)」「いも類」などの主食は、運動する2~3時間くらい前に済ませておきたいです。
また、単糖類であるブドウ糖や果糖、二糖類であるショ糖(砂糖)などが含まれているスポーツドリンクやエナジージェル等では、消化吸収が早いため、運動する前や、運動中に摂取してもいいでしょう。
ただし、糖質を摂り過ぎてしまい血糖値の上昇の後にくる低血糖には十分注意するようにしましょう。
なお、スポーツ用のフーズやドリンクの中には、マルトデキストリンなどのすぐに消化吸収されるものや、パラチノースなどのゆっくりと持続的に消化吸収されるものがあります。
自分の取り組む競技やトレーニング内容によって、使い分けると良いでしょう。
糖質を摂取するポイントとして「糖質の種類」があります。
3.GI値
糖質を摂取するポイントとして「GI値」があります。
GI値とは「Glycemic Index」の略であり、食事をした後の血糖値の上昇度を表す指標のことです。
食事をすると、糖質(ブドウ糖)が消化吸収されて血糖が上昇しますが、このときの「血糖値が上昇する程度」は食品の種類によってさまざまです。
食事をした後の血糖値の上昇度を表す指標のことを「GI(Glycemic Index)値」といいます。
GI値が高い食品「高GI食品」を食べると、食後の血糖が急激に上昇します。
そして、血糖値を下げる作用のあるインスリンというホルモンが分泌されて、血糖値の急下降が起こる「血糖値スパイク」と呼ばれる現象が起こります。
なお、血糖値スパイクの健康面への影響として「糖質の過剰摂取につながる」「低血糖症状」、「生活習慣病」「認知機能の低下」「免疫力の低下」などのリスクが上がるなどがあります。
血糖値スパイクを抑えるコツとして「糖質を最後に食べること」「よく噛んで食べること」「低GI値の食品」「栄養バランスの良い食事」などがあります。
トレーニングや運動を行う前後など、すぐに糖質が必要な時には、「GI値が高いもの」を、反対にゆっくりと糖質を補給したい場面では「GI値が低いもの」を選びましょう。
一日全体の流れを見た場合、トレーニング前後に糖質を多めに摂取すること、間食などで食事回数を増やすなどの工夫によって、血糖値スパイクをおさえながら糖質を摂取することができます。
糖質を摂取するポイントとして「GI値」があります。
まとめ
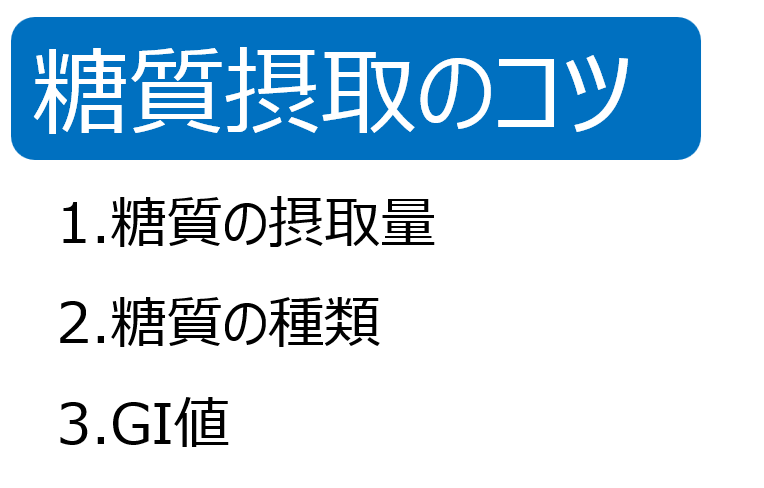
今回は「糖質を摂取するポイント」について説明しました。
この記事によって「糖質を摂取するポイント」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/
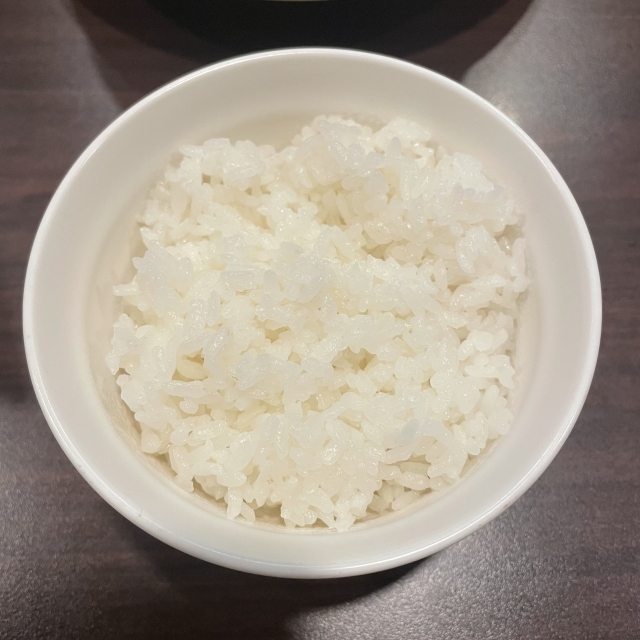









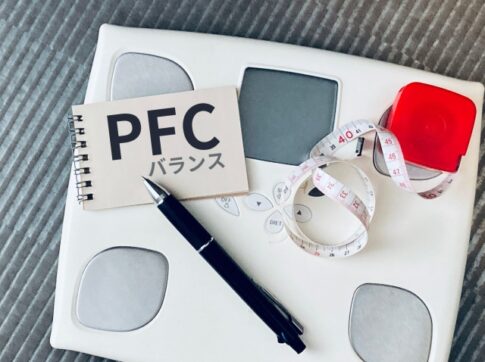




コメントを残す