結論ですが
肝臓に優しい食品栄養として「しじみ」「ごま」「もやし」「みそ」などがあります。
この記事は「肝臓について知りたいヒト」に向けて書いています。
食事・栄養に対する疑問・悩み・不安などが解決できればと思っています。
この記事を読むことで「肝臓に優しい食品栄養」についてわかります。
肝臓に異常を指摘されましたが、どのような食事をすればいいですか?
このような疑問にお答えします。
健康診断などで血液検査をすると、ほぼ必ず肝臓の数値も測定するかと思います。
肝臓の数値が悪いと、どのような影響がおこるか不安になるかもしれません。
沈黙の臓器といわれる「肝臓」
肝臓にダメージが加わっても、わかりやすい症状は現れないため、長年、肝臓を痛めつけているケースも多々あります。
肝臓は実に様々な働きをしています。
そして、我々が日常生活を送るうえで、肝臓はなくてはならない存在です。
では、肝臓に優しい食品栄養には、どのようなものがありますか?
ということで、今回は「肝臓に優しい食品栄養」について説明していきます。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/
まとめ
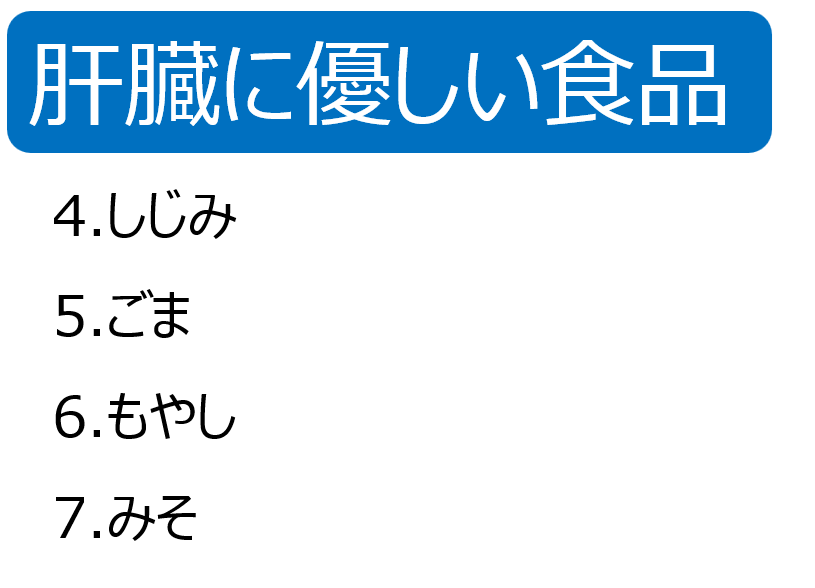
4.しじみ
肝臓に優しい食品栄養として「しじみ」があります。
昔から肝臓が悪くなったら、しじみのみそ汁を飲むとよいと言われてきました。
しじみには「タウリン」というアミノ酸の一種が含まれています。
タウリンは、アミノ酸の一種で、たんぱく質が分解される過程で生成される物質です。
タウリンには、肝臓の解毒作用をサポートする働きがあり、肝臓を守ってくれる働きがあります。他にも、体温調整機能、キズの修復促進、血圧の維持、水分バランスの調整、コレステロールの改善などの作用が期待できます。
肝臓に優しい食品栄養として「しじみ」があります。
5.ごま
肝臓に優しい食品栄養として「ごま」があります。
ごまには「セサミン」という成分が含まれます。
セサミンは、体内に吸収されて肝臓まで届くと、肝臓で代謝されることで高い抗酸化作用を持つようになります。この結果、肝臓の活性酸素を取り除いたり、アルコールの分解を促進したりと、肝臓の負担を和らげてくれるのです。
なお、セサミンとビタミンEを併用することで、肝臓が保護され、血中の悪玉コレステロール値の上昇を抑えることが確認できた研究結果もあります。
セサミンは、ゴマに含まれる栄養成分の一種で、ゴマ1粒にわずか1%未満しか含まれていない稀少な成分です。
ゴマに含まれる「ゴマリグナン」という抗酸化物質の一種で、セサミンはゴマリグナンの中で最も多く含まれています。
肝臓に優しい食品栄養として「ごま」があります。
6.もやし
肝臓に優しい食品栄養として「もやし」があります。
一見、栄養がなさそうにみえるもやしですが、実はビタミンB1、B2などのビタミンB群が含まれています。
肝臓の機能が低下すると、ビタミンの貯蔵能力が低下するため、ビタミンを十分に補給することが必要です。
とくに、ビタミンB群は肝機能を正常化させる働きをします。
また、もやしには良質な植物性たんぱく質を含んでいるので、肝臓を元気にしてくれます。
肝臓に優しい食品栄養として「もやし」があります。
7.みそ
肝臓に優しい食品栄養として「みそ」があります。
みそは、大豆を蒸すか煮るかしたものに、こうじと食塩を加えて、発酵、熟成させた調味料です。
みその原料である大豆には、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルなどが豊富に含まれます。
さらに、こうじの働きで発酵することによって、これらの物質の消化吸収が良くなり、栄養価がいっそう高まります。
みそには肝臓の解毒機能を高め、がんを予防する効果があるといわれています。
繰り返しですが、昔から肝臓が悪くなったら、しじみのみそ汁を飲むとよいと言われてきました。
肝臓に優しい「しじみ」と「みそ」の食品の最強の組み合わせになります。
肝臓に優しい食品栄養として「みそ」があります。
まとめ
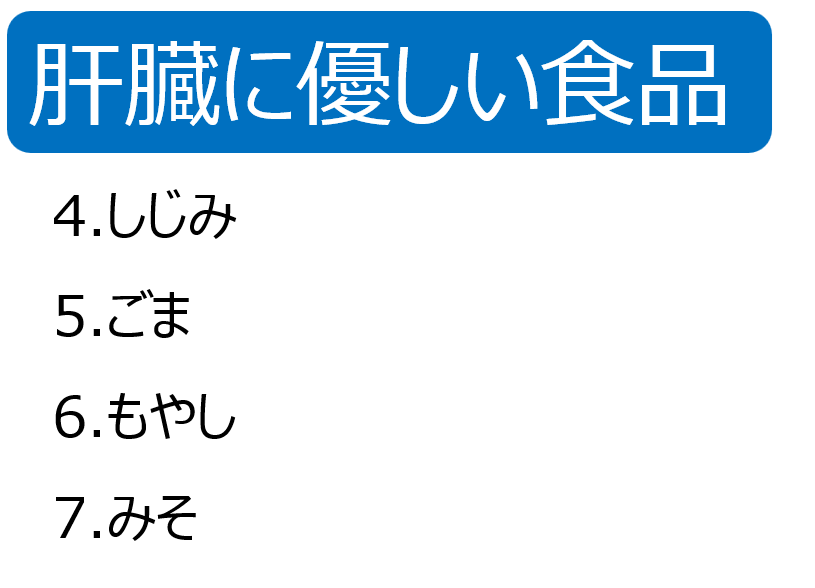
今回は「肝臓に優しい食品栄養」について説明しました。
この記事によって「肝臓に優しい食品栄養」についての理解が深まり、一人でも多くの人に役立つことを願っています。
「宮の沢スマイルレディースクリニックホームページ」
https://www.miyanosawa-smile-lc.com/




コメント